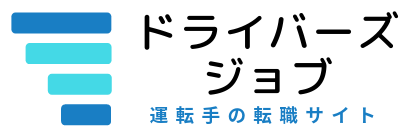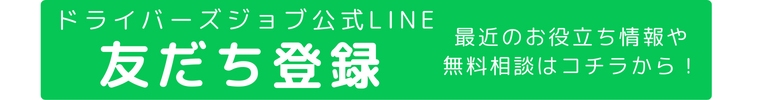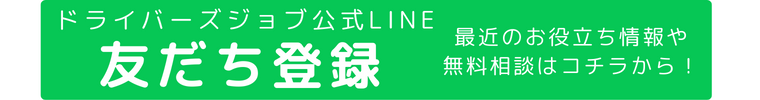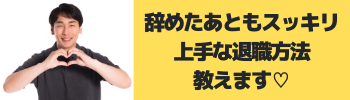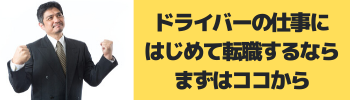積載車とは
積載車とは、乗用車や小型トラックなどを運搬する専用車両のことで、キャリアカーとも呼ばれます。
積載車は3種類あり、1台積載用のローダー、2~5台積載の単車に加え、6台以上積めるトレーラーに分けられます。
ローダーは、小型トラックや中型トラックの荷台を改造して作られます。一方、単車は大型トラックをベースに、二段式の架装が組まれます。最も運転が難しいトレーラーは、トラクターでけん引される構造を持ち、最大で8台積みのトレーラーまで存在します。
積載車の運転に慣れるのには時間がかかる?
積載車の比率はトラックのわずか1%で、タンクローリーよりもレアなトラックです。
長く運送業界で働く人でも、車を運んだ経験がある人は少なく、運転のコツを教わったり練習をする機会は限られるので、積載車の運転に慣れるには時間がかかるでしょう。
しかも積載車は、自動車という巨大な重量物を運ぶわけですから、運転も駐車も難しいです。乗せる台数が多ければ重量変化も気になりますし、ときには積んだ車両の高さが全高を超える位置まで露出することもあるからです。
積載車の運転が難しいと言われるところ
全長が長く小回りがきかない
積載車に採用されるトラックは、基本的にワイドキャビンでロングホイールベース仕様です。
小型トラックの日野デュトロでも車幅は2mあり、荷台は5m前後もあります。よって積車時・空車時を問わず、交差点での右左折といった通常の進路変更ですら、普通の小型トラックのような小回りは期待できず、運転が難しいポイントとなります。
特にカーブのきつい道では、対向車線へのはみ出しに注意し、狭い路地を運転するときは、家の屋根や塀、標識等への接触にも注意しましょう。
高さ制限にも注意が必要
特に二段積みの積載車を運転する時は、高さ制限に注意です。
積車の状態であっても、道路法に基づく車両制限令の3.8m以内(高さ指定道路では4.1m以内)を超過すると違反となります。
たとえ制限以下でも、2.5mある標識やその他看板類よりも全高が高ければ接触のリスクも増加しますし、高架下のトンネルの高さは3.1m程度なので二段積みは通行できません。
トラックで普通に通れていたのに積載車ではぶつけることもあるくらい、運転は難しいです。
車体が大きいと死角が多い
積載車は、自動車を安全に輸送するために車幅が広く荷台が長い作りです。そのため積載車の車体は同型のトラックよりも一回り大きく、おのずと死角も増えます。
さらに積載車は、積んだ車両が壁となり、真後ろが見えません。よって、車載カメラを付けたり、窓を開けて目視で確認するなどの工夫が求められます。
大きな車体ゆえに後部状況を把握しづらいのは、積載車の運転が難しいとされる理由の一つです。目的地に到着しても駐車場所に無事停車するまでは油断大敵です。
車体が大きいと内輪差と外輪差が大きい
自動車がカーブを曲がると、前輪と後輪が描く軌道に差が生じます。内側の差を内輪差、外側の差を外輪差といいますが、これらはホイールベースが長くなるほど大きくなります。
内輪差が大きいと、左折時にバイクや歩行者を後輪で巻き込む危険があり、外輪差が大きいと、対向車線の車に接触する原因となります。
積載車はホイールベースが長いだけでなく、後輪より後ろの荷台のはみ出し(リアオーバーハング)も大きいので、いわゆるケツ振りが出やすい結果、運転が難しいのです。
運搬物が高価でプレッシャーを強く感じる
積載車の運転が難しい理由は、車体の大きさのせいだけではありません。積載物はこれから販売されようとする自動車、つまり高価な品物で傷はご法度というプレッシャーも運転手の肩にのしかかります。
積載車で物損事故を起こせば、運送会社は当然、賠償責任を問われますし、ドライバーに明らかな過失があれば、費用の一部を負担しなければならない場合もあります。
積載車の運転のコツ
事前にルートをしっかり確認しておく
余裕を持って積載車の運転を安全に行うコツは、まず事前のルート確認にあります。
トレーラーの特殊車両は、通行許可の取れた道路以外は走行禁止です。よって出発地(自動車工場など)から、目的地(販売店や港など)までの指定ルートを頭に入れ、高さ制限もチェックしておくことが重要です。
たとえ単車やローダーでも油断は禁物です。カーブでの接触事故を避けるために、無理に最短ルートで向かおうとするのではなく、道路幅が広く、右左折の回数が少ないルートを選択しましょう。
スピードを出しすぎない
トラックの運転席は乗用車よりも高い位置にあるため、速度感覚が鈍り、思った以上にスピードを出してしまいがちです。
特に積載車の場合は運搬物が車両なので、スピードが出た状態から急制動させると、反動でタイヤが動いて物損事故に繋がりやすいのです。かといって、あらかじめ車両をガチガチに固定することは、ボディに傷が付くため具合が悪いです。
積載車の運転で身につけておくべきコツは、焦らず飛ばさず、慎重なペダル操作を心がけることです。
ハンドルはゆっくり回す
積載車の運転に『急』が付く動作は禁物です。ハンドルを急に切ると荷台に遠心力が強くかかるため、最悪の場合、積んだ車両ごと横転します。
カーブの走行時は、進行方向の先まで良く見て、余裕を持ったハンドル操作を行うことが大切です。
交差点への進入時には内輪差を考慮して、ハンドルは急に回さず、乗用車よりもやや遅らせ気味に切り始めるのが積載車の運転のコツです。
ただしタイミングを外すと曲がりきれないので、横乗り教習などでベテランのハンドルさばきを学習しましょう。
バックカメラを設置して死角をなくす
積載車を安全に運転するコツは、できるだけ死角を減らすことです。しかし、積載車両が後方視界の妨げとなるので、ルームミラーを頼りにすることはできません。
そこで、少しでも後ろの状況が見やすいよう、積載車には前方に張り出した大きなサイドミラーとアンダーミラーが標準装備されています。
ただしミラー類だけでは真後ろの死角は解消されないので、バックカメラの装着をおすすめします。積載車のように全長が長いトラックには、配線処理不要の無線タイプが手軽で便利です。
こまめにメンテナンスをする
積載車の構造は複雑です。1台ごとにカスタムされた特殊な荷台を持つからです。ゆえに、一般のトラック整備として欠かせないタイヤチェックやオイル交換はもちろんのこと、荷台のスライド機構や道板(歩み板)の開閉動作も日々確認することが大事です。
こまめなメンテナンスは、車両寿命を伸ばし、維持費用を抑える効果があるだけでなく、トラブル箇所の早期発見にもつながり、事故を未然に防ぐことができます。
積載車の安全運転を継続するコツは、日常点検をサボらないことです。
積載車は積み下ろしも難しい?
積載車の積み込み手順そのものはシンプルです。
- 荷台後部の道板をガイドラインに合わせてセット
- 上段から順に車両を積み込み
- 車の牽引フックにベルトやワイヤーで固定
さらに、ラジコンを使ったリモート操作が可能な機種も増えているため、積み下ろしに力作業はありません。
ただし、輸送する自動車は高価である上に大きさも様々です。傷を付けずに積載するには経験とノウハウが必要なのが難しい点です。
雨などの悪天候時は道板が滑るため、積み下ろしは特に慎重に行います。
積載車の積み下ろしの際に確認しておきたいこと
積載車へ積み込みを行うときの確認事項は次のようになります。
- 積載する車両の汚れや傷みのチェック(トラブル防止のため)
- 道板とガイドラインが一直線上になっているか(ズレがあると脱輪の恐れあり)
- タイヤがタイヤストッパーの溝に適切に埋まっているか
- 車両と積載車がワイヤーやロープで繋がれ固定されているか
- 隙間は適切か(積載車と積載車両の隙間は5cm以上、積載車両同士の隙間は10cm以上あける)
- 積み込み完了後、道板を格納したか(折りたたみや格納せずに走行すると道路運送車両法違反)
また、積載車から積み降ろしをするときにも確認事項があります。
- 安全に下ろしきれるスペースの確保
- 道板を規定の角度まで展開できる路面状態か(雨雪時は特に注意)
- 積載車の損傷チェック(積み下ろしで発生した傷みがないか)
積載車を運転するのに必要な免許
ローダーの運転に必要な免許
積載台数1台もしくは二輪車の積載が可能なローダーの運転に必要な免許は下記のいずれかです。
- 車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満の準中型免許
- 8トン限定中型免許(平成19年6月1日までに普通免許を取得した者)
平成19年と平成29年の2度の免許制度改正により、普通免許の重量区分が徐々に縮小しました。現行の普通免許で運転できる車両は、車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満の車両のみです。
フラトップやエスライド、ユニックキャリアなどローダーの主力車種はいずれも最大積載量2t以上であるため、たとえ空荷であっても普通免許ではこれらの積載車を運転できません。
単車の運転に必要な免許
単車の積載車は、積載台数2台以上かつ2段構造なので、ローダーよりもサイズ・重量ともに大きく、種類も豊富です。そこで、単車の運転に必要な免許を調べるときは、実車の最大積載量と車両総重量に注目します。
例えば、2~3台積みの単車の場合、最大積載量は3トン前後です。この数値だけを見ると、準中型免許でも運転可能に見えますが、車両総重量が8トン近くあるため、準中型免許では運転できず、単車の運転には最低でも中型免許が必要だと分かります。
そして大型トラックのシャシーを利用した4~5台積みの単車になると、最大積載量が8トン以上あるので大型免許が必要です。
トレーラーの運転に必要な免許
積載台数6台から最大で8台もの自動車を運搬できるトレーラー積載車の運転に必要な運転免許は、大型免許です。大型免許があれば、最大積載量6.5トン以上、車両総重量11トン以上のトラックを運転できます。
ただし、トレーラー積載車の運転は、750kgを超える車両をけん引するので、大型免許に加えて牽引免許も取得しないといけません。
牽引免許は普通免許があれば18歳から取得できますが、大型免許の取得条件は21歳以上で、かつ普通免許などで3年以上の運転経歴が必要です。つまり、トレーラータイプの積載車を運転できるようになる年齢は、最低でも21歳からです。
積載車を扱う上で必要となる運転免許以外の資格とは
小型移動式クレーンの免許
レッカー車でよく見かけるような伸縮や旋回可能な小型移動式クレーンの操作には、吊り上げ荷重1t以上5t未満の小型移動式クレーン運転技能講習の修了者であることが必要です。
取得方法は、学科と実技の受講および修了試験です。修了証(国家資格)を3日で取得できます。
小型移動式クレーンは、積載車にも架装オプションで取り付けることができます。吊り上げ荷重は、積載車の大きさによらず2.9tと共通なので、クレーン免許の保有者は積載事業者への就職にも活かせます。
巻き上げ機特別教育
巻き上げ機とは、エンジンなどの動力を用いワイヤーを巻き上げる機構、すなわちウインチのことです。
事故などで横転し、自走不能になった車両はクレーンで元の姿勢に戻してから、搭載されたウインチで積載車に積み込むという手順を踏みます。
事故処理用途で活躍する積載車に必ず搭載されているウインチの操作は、国家資格の巻上げ機運転者が担当します。
巻き上げ機の免許の取得方法は、巻き上げ機特別教育(学科+実技)を受講し、平易な確認試験に合格することです。
「働いても給料や条件があまりよくならない」、「体力的にも労働時間もしんどくなってきた」、「将来が不安」、でも”いい仕事ってないよなぁ”と感じたりしていませんか?
もしそうなら、ドライバー不足の今は絶好のチャンスです!
ご存じかもしれませんが、ドライバー不足でどこの企業も人を欲しがっているため、これまで考えられなかったような高年収・好待遇の案件が増えてきています!
なので、もしあなたが最近になっても「あまり年収や待遇がよくならないなあ」と感じるなら転職すれば年収・条件アップの可能性はかなり高いです!
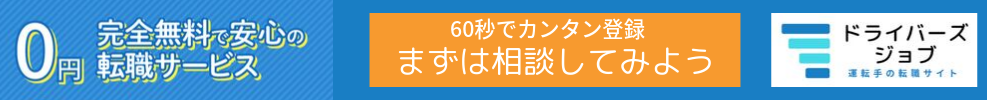
【LINEでドライバーの転職相談】
もちろん転職やお金が全てではありません。慣れた環境や仕事があれば長時間労働や低い年収も気にしないという考えもあります。
ただ、そこまで本気で転職を考えたりはしてないけど、「一応、ドライバーの年収や労働条件って世の中的にはどの位がアタリマエなのか興味はある」、というのであれば情報収集するのは得はあっても損はないでしょう。
ただ、ドライバーの仕事は忙しいのでじっくり探す時間はなかなか取れないものです。ホームページに書いてあることが本当かどうかあやしいと感じるドライバーさんもいます。
それなら、ドライバーズジョブの転職サポートサービスに仕事探しを任せてみませんか?
- 転職するしないに関係なく完全無料でサポート
- 電話で希望条件を伝えて待っているだけで好条件の仕事を探してもらえる
- もし応募したくなったら、履歴書や面接のサポート、条件交渉も手伝ってもらえる
ので、仕事を探す方にはメリットしかないようなサービスです!
ドライバーズジョブはドライバー専門のお仕事探しサービスなので運送業界や仕事内容に詳しく、ドライバーや運送業界で働こうと考えるみなさんを親身になってサポートします!
登録はもちろん無料で、気軽な悩みから仕事探しまで何でも相談してみてください。![]()
また、「ちょっともうドライバーは疲れたなあ」「他の仕事もやってみたいなあ」という方もいらっしゃると思います。
今の世の中はどの業種も人手不足で年齢に関わらず未経験者も積極活用中です。ドライバー経験者の方は体力もある方が多く採用でも有利なため、全く別の業界で活躍される方も多くいらっしゃいます。
人材紹介サービスはどの会社も転職希望者に費用は発生しないので(採用企業がコストを支払うため)、気になった方は話だけ聞いてみるのもアリでしょう。